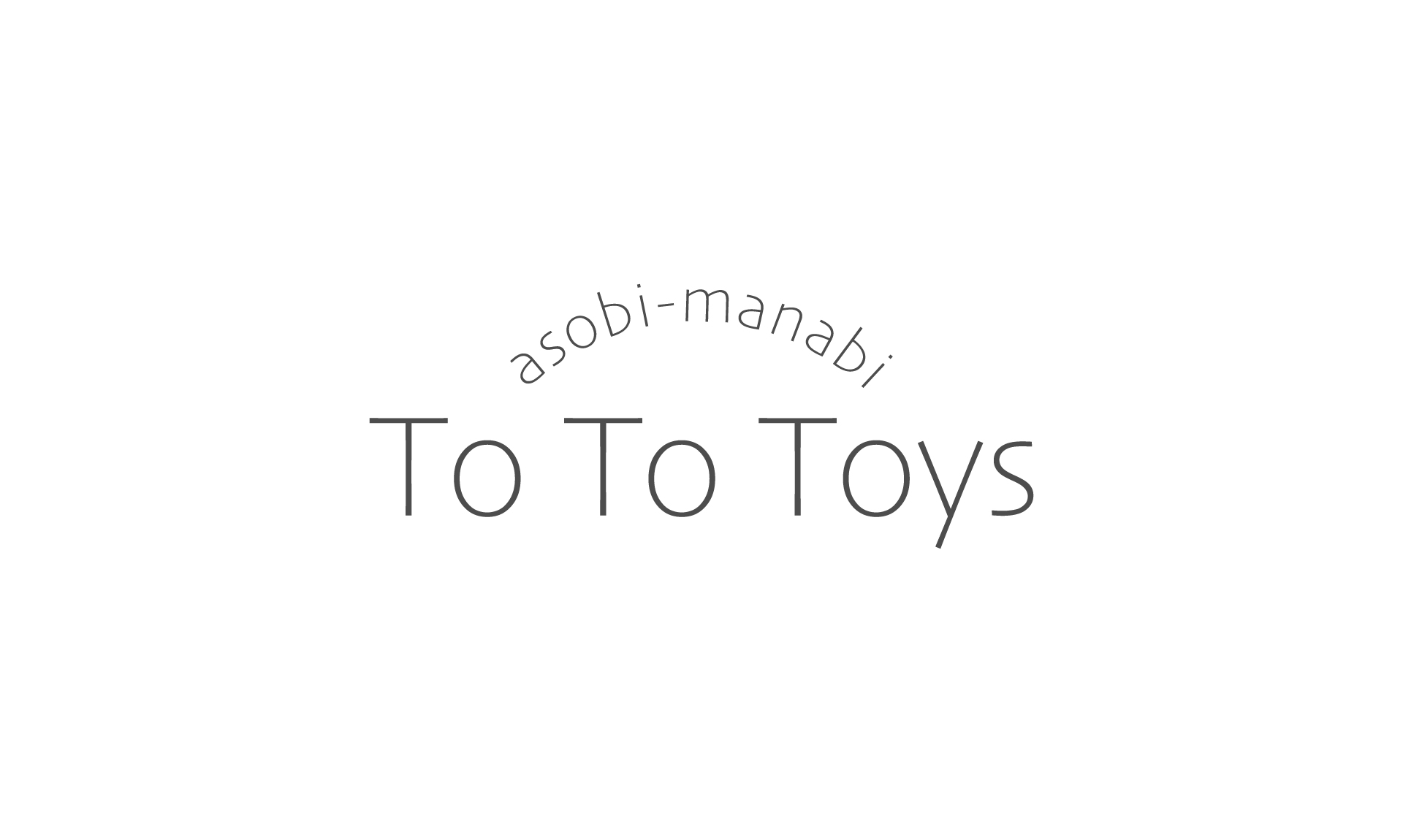こちらの記事では、寝かしつけのプロである保育士さんは普段どのようなことを意識しながら子どもたちの寝かしつけを行なっているのか、上手な寝かしつけの方法やコツを紹介していきます。
家庭での育児の参考にしてみてくださいね。

なかなか寝ない子育ては辛い|保育士さんの子ども寝かしつけテクニック
「睡眠は重要な役割を果たす」その効果は?
赤ちゃんや幼児の成長において、睡眠は極めて重要な役割を果たします。生後間もない赤ちゃんは、1日の大半を寝て過ごすことで成長しますが、0歳~2歳頃にかけては、身体の機能が向上する時期であり、午前中から活発に動き回り、たくさん遊びます。このような成長期において、保育園でお昼寝をさせることは、子供たちの体力を回復させるだけでなく、心身をリラックスさせる重要な手段です。
睡眠は体力の回復だけでなく、「集中力」「記憶力」などの向上にも繋がります。お昼寝をすることでリフレッシュし、集中力が維持されるとともに、午前中の活動や学びの内容をより良く記憶することができます。このため、「寝る子は育つ」と言われるように、お昼寝は子どもの心身の成長や脳の発達に欠かせない要素です。また、お昼寝は毎日同じ時間に行うことで、子どもの生活リズムを整える役割も担います。
なかなか寝てくれない。すぐに起きてしまう。
子どもの睡眠には個人差があります。全ての子供がすんなりお昼寝をするわけではなく、「おねんねモード」にならない、すぐに起きてしまう、抱っこから降ろすと起きてしまうなど、様々なケースがあります。
成長に伴い、お昼寝が必要でなくなる時期もありますが、それまでは子どもの個性に合わせた寝かしつけが求められます。
保育園で上手に寝かしつけるコツやテクニックは様々です。
それでは、保育士さんが実際に行なっている寝かしつけのテクニックをご紹介していきます。
保育士実践‼︎寝かしつけテクニック
子どもを寝かす際には、「ここにいるから大丈夫だよ」という安心感を与えることが基本です。保育園では、子供が安心して眠れる環境作りや、様々な寝かしつけのテクニックが実践されています。
例えば音楽やオルゴール、子守歌を聞かせて心が落ち着かせたり、添い寝や耳元での呼吸を合わせること。背中トントンや眉間のマッサージ(目と目の間、鼻筋の上を指で上下に優しく撫でてあげる)、絵本やお話を読むことも効果的と言われています。
2歳以上になると、言葉の理解が進み、寝かしつけるコツも変わってきます。子供の個性や成長段階に合わせて、適切な寝かしつけを行うことが重要です。
寝かしつけテクニック詳しくみてみましょう
●音楽・オルゴール・子守歌
リラックスした雰囲気を作るために、ゆったりとした音楽やオルゴールのメロディを流すと効果的です。また、一般的な子守歌だけでなく、子供が安心する歌を静かに歌ってあげるのも良いでしょう。心地よい音楽が眠りを誘い、子供たちがぐっすり眠るのを助けます。
●一緒に寝る・耳元でささやく
子供たちは身近な存在と一緒にいることで安心します。目を合わせて子供の傍にいたり、耳元で呼吸の音を聞かせながら優しくささやくことで、子供たちは安らかな眠りにつきやすくなります。
●マッサージ・背中トントン
子供の背中を優しくトントンしたり、さすったりすることで、子供たちの体に温かみを感じさせることができます。また、頭や額をさすることでリラックスさせ、眠りに誘います。
●抱っこ・おんぶ・おくるみ
寝かしつけに苦戦している子供は、抱っこやおんぶをしてあげると落ち着くことがあります。全身をおくるみで包むことで、子供たちが安心して眠りにつくことができます。おくるみに包まれることで、母親のお腹の中にいた時の安心感を思い出し、泣き止むこともあります。
●絵本やお話を読む
子供たちは優しい声に包まれることで安心し、眠りにつきやすくなります。傍にいて絵本を読んであげたり、優しく語りかけることで、子供たちの心が落ち着き、安らかな眠りにつくことができます。
以上が実際に保育士さんたちが行なっている子どもの寝かしつけテクニックです。難しいものはなく今日からご家庭でも実践できることばかりですね!
お昼寝を嫌がる…家庭と保育園の連携が大切

子どもがお昼寝をしたがらない場合には、外遊びを多くしたり、子供の個性や状況に合わせた対処法を取ることが必要です。焦ったり怒ったりせず、子どもの成長に合わせた見守りが重要です。
生活習慣の見直しも重要であり、カラダを動かす遊びや日光に当たる時間を増やすことで、子どもの睡眠リズムを整えることができます。保護者との協力や相談も大切であり、子どもの健康的な睡眠環境を整えるためには、家庭と保育園が連携して取り組むことが欠かせません。
子どもをよく観察して対処法を考えよう
お昼寝は、子どもの成長と健康にとって極めて重要な要素です。しかしながら、子供が寝ないという場合には、その背後に様々な理由があるかもしれません。
例えば、先述したように、周囲の環境の変化や子供の個性、成長段階などが影響を与える可能性があります。そのため、子供が寝ないと感じた場合には、一概にその子が寝るべきだと考えるのではなく、その子の状況や環境をよく観察し、対処法を考えることが重要です。
子どもが寝ないと感じたら日常生活を見直そう
子どもが寝ないと感じた場合には、まずは日常生活の見直しから始めることが良いでしょう。
十分な運動や外遊びの時間を確保することで、子どもの体力を消耗させることができ、自然と眠りの質が向上することがあります。
また、子どもの寝る前の環境やルーティンを見直すことも効果的です。静かで穏やかな環境を整え、寝る前のリラックスタイムを確保することで、子どもが安心して眠りにつくことができます。
例えば、寝る前には絵本の読み聞かせを行う。その後電気を消して「おやすみなさい」というルーティンを継続すると、子どもの寝る習慣が身についてきます。絵本でなくても、時計の針が12のところに来るまでお話をしようね。と前置きをつくってから寝かしつけるのもの良い方法ですね。
また、電気を消す役割を子どもに与えてあげたりと、親が「一方的に子どもを寝かす」のではなくて、子どもが自ら寝ることができるような流れを作ってあげるのも大切なことです。
なかなか寝ようとしない時には、無理に寝かそうとせずに子どもとコミュニケーションを取りながら、その理由を探ることが重要です。また、子どもが不安やストレスを感じている場合には、その解消策を考え、子どもが安心して眠ることができる環境を整えることが必要です。
その他の睡眠の記事はこちら↓
寝かしつけを成功させるには日常生活の中での刺激も大切です。特に遊びは子どもにとって学びであり、その道具であるおもちゃ選びは非常に重要です。最後に私がおすすめするおもちゃメーカーをご紹介してこちらの記事を終わりにしようと思います。
最下部の画像をタップするとメーカーのホームページをみることができます。ぜひ一度ご覧くださいね!
子どもと過ごす楽しい時間におすすめのおもちゃメーカーがある

はじまりは幼児教室から。
GENI(ジェニ)
安心安全の商品を提供し続ける創業35年、日本屈指のおもちゃメーカーです。
私は現在、知育玩具のサブスクリプションサービス事業に携わっているため、普段から様々な玩具メーカーの数百種類のおもちゃに囲まれて仕事をしています。
時にはお客様の情報を元におもちゃを選定したり、デザイン制作のために様々なおもちゃを実際に手に取ってみたり。
そんな中でいつも感心してしまうのがこちらのGENIというメーカーです。
幼児教育の現場から「良いおもちゃ」届けメーカーです。
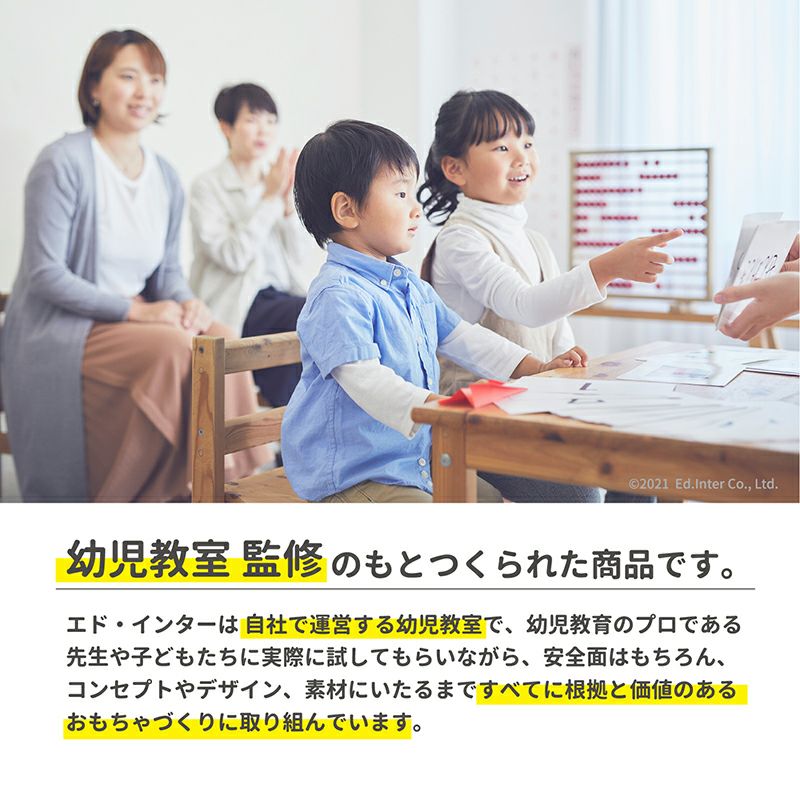
私たちのものづくりの原点は、1988年に設立した幼児教室。
GENI ホームページより引用 https://ec.ed-inter.co.jp/f/about
教室には0歳から小学生までの子どもが集い、五感を使った遊びを通して、
感受性や創造力、思考力、コミュニケーション力を養っています。
私たちはこの教室で、幼児教育のプロフェッショナルの先生や 子どもたちに実際に製品を試してもらいながらともに価値あるおもちゃづくりに取り組んできました。
だからGENI(ジェニ)のおもちゃには、安全面はもちろん、 製品コンセプトやデザイン、素材にいたるまで、 すべてに「根拠」があるのです。
現代は安くて大量生産のおもちゃが身近にあります。
しかし、大切な我が子が使うもの。
おもちゃは子どもたちにとっての学習のための大切な道具ですから、「長く使える良いおもちゃ」を与えたいですよね。
GENI(ジェニ)のおもちゃは子どもが楽しく遊べる要素が詰まったおもちゃです。
ぜひ一度手にとってみてくださいね!